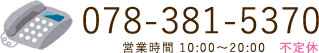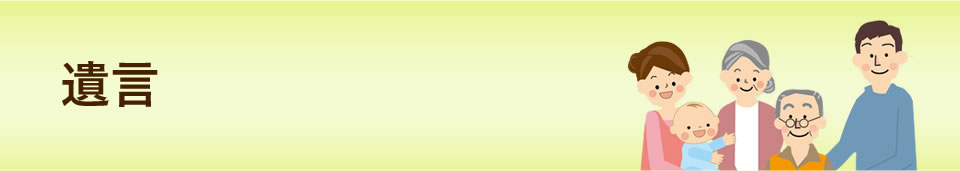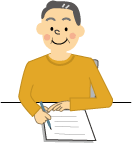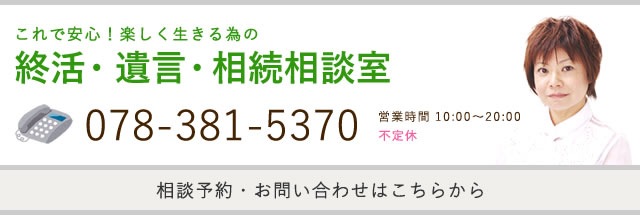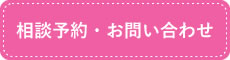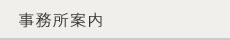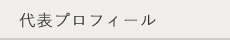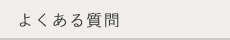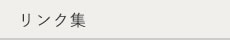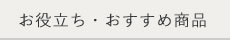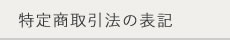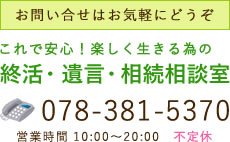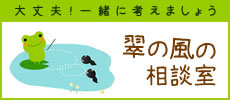- ホーム
- >
- 遺言に関する業務:公正証書遺言
公正証書遺言
公正証書遺言
本のタイトルに「ないと困る遺言あっても困る遺言」と言うのがあります。
思わず、そうだ!と叫んでしまいそうになってしまいました。
これは、名コピーです。
【 なぜ公正証書なのか 】
辰巳総合法務事務所では、自筆よりも公正証書の作成を強くおすすめしています。
なぜなら、自筆遺言や法務省の保管制度には限界があり、せっかくの遺志が反映されない危険があるからです。
【 自筆証書遺言と保管制度の限界 】
1. 書くこと自体が大変
自筆遺言は「全文を自分で書かなければならない」のが原則です。
財産目録は添付資料で代替できますが、それ以外は自筆。目が悪くなり、手元が震えるようになった高齢者の場合は、大きな負担となります。
しかも誤字・訂正で形式を外れると無効になりかねません。
「手軽」どころか、実際にはリスクの大きい作業です。
2. 本人の状態が争点になる
遺言は書いた当時に「判断能力」があったかどうかが争われやすいものです。
特に高齢や認知症の疑いがある場合、相続人から「書けるはずがない」と主張され、裁判になる例が少なくありません。
3. 遺言の存在が失われるリスク
誰も存在を知らないまま相続が進む
災害や火事で消失する
見つけても隠される可能性がある
こうしたリスクも自筆遺言にはつきまといます。
【 法務省の「自筆証書遺言保管制度」の限界 】
この制度を使えば、形式不備はほぼ防げます。法務局が厳しくチェックするからです。
また、名前のとおり「遺言を確実に保管してくれる」点は大きなメリットです。
しかし、それでも――
内容の有効性は保証されない
本人の意思能力までは確認されない
保管してくれるだけで、争いを完全に防げるわけではない
【 公正証書遺言なら安心できる理由 】
法律構成に矛盾がない
公証人が法律に従って作成するため、要件不備や条項の矛盾がなく、有効性が担保されます。
全文を代筆し、読み聞かせで意思確認
公証人が代筆し、内容を読み聞かせて本人の理解を確認します。
→ 「認知症で書けなかった」と争われにくい。
原本を公証役場で保管
隠匿・偽造・災害による消失の心配がありません。
裁判でも強力な証明力
万が一争いになっても、有効な証拠として扱われます。
遺言公正証書:財産額に応じて公証人の手数料が変わります(→日本公証人連合会HPをご参照ください)。
※ 別途、謄本代・証人日当・郵送代などの実費が必要になります。
【 ではなぜ士業を挟むのか? 】
「公証役場は自分で行けるのでは?」と思う方もいるでしょう。
確かに手続き自体は可能です。
しかし、安心できる公正証書に仕上げるためには、士業の役割が欠かせません。
公証人は中立的立場
依頼者の意向を「そのまま」反映してくれるわけではなく、法律に合わない部分は修正されます。
矛盾点を事前に整理できないと危険
依頼者の希望が複雑な場合、表現次第で無効になることもあります。
私たちがいる意味
ご依頼者様から丁寧にお話を伺う中で、矛盾や抜け落ちた課題が浮かび上がることがあります。
それを同時に解決しなければ全体の整合性が崩れてしまうことも少なくありません。
しかし、そのまま公証人にお願いしても、公証人は気づきません。
だからこそ、私たち士業が間に入り、
意向を整理して法的に有効な形に整え
公証人との打ち合わせをスムーズに進め
齟齬を極力避けて、安心できる公正証書に仕上げます。
【 まとめ 】
自筆や保管制度にも一定のメリットはありますが、争いを防ぐ力には限界があります。
安心して遺志を残すためには、公正証書遺言が最も確実で安心度の高い方法です。
辰巳総合法務事務所では、ご依頼者様のお話をじっくり伺い、
ご希望を法的に矛盾のない形に整えて公証人と連携し、
安心できる公正証書作成を全力でサポートいたします。
※ 遺言作成にかかる費用は、内容や状況によって異なります。詳細は[報酬案内]をご覧ください。
※ ! 遺留分減殺請求についての民法改正がありました。(2019年)
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺言によっても侵し得ない遺留分という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求」といいます。
この遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変わりました。
何がかわったか、ピンとこないかも知れませんがこれはとても大きな改正で、前の法律では(減殺請求))物権的効果を生じた目的物(例えば家)などが共有物になったために共有物の分割問題がおこり(元々遺留分を請求する立場とされる立場でもめている場合が多い)その解消には時間とお金労力がかかっていました。それを今回の新法では物(家)そのものではなく、金銭債権として(家そのものではなくその評価を金銭にかえて)権利を行使することになりました。
この権利の行使は1年以内にします。
そしてこの金銭債務の履行請求をしてお金を支払ってもらいますが、この消滅時効は5年になりますので注意してください。
ここでも債権法の改正があり(2020年4月1日施行)旧法では10年であったものが5年に短縮されています。
また遺留分算定の基礎財産に加える相続人に対する生前贈与を10年以内にされたものに限定されています。
以上のようなことは遺言を作成するうえで考慮しなければならない事項になってきますので専門家と協議の上作成されることをお薦めします。